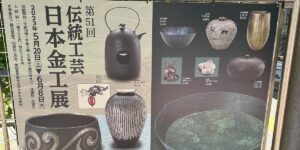こんにちはIMULTA彫金師の上谷です。
今回は過去に行った美術展の紹介。
彫金の独学で一番困るのはタガネで彫る練習をして結局どういったものが作れるかという事がイメージしづらいという事があります。
彫金学校や彫金教室に行っている方でも同じかもしれませんが、そういった時は美術展に行って実際に先人がどういったものを作っていたかを見るのが一番手っ取り早いのでオススメです。
初心者の方が彫金の知識を増やすために役立つ電子書籍を用意しています。

彫金のちゃんとしたものを見たいのであれば根津美術館の鏨の華に行けばいい
結論から言うと根津美術館に収蔵されている光村利藻の刀装具コレクションを見るのが一番手っ取り早いです。
2017年の開催を最後に行われていないようですが、明治期の大金持ち光村利藻氏が収集した300点以上の一大コレクションのうち約1200点が所蔵されています。
動画でも解説してますのでご覧ください。
高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。

\IMULTAの読む彫金教室のサポートをお願いします/
いただいたご支援はブログとYOUTUBEチャンネルの運営に当てさせていただきます。
刀装具の美術展はまれ
探せばあると思いますが大々的に刀装具の展示会が行われることはまれだと思います。
近年は刀剣乱舞の影響で若い女性も刀に興味を持っている影響で「刀」の展示はあっても「刀装具」の展示会というのはあまり聞きません。
次回いつ開催されるかわかりませんが「根津美術館に刀装具の一大コレクションが収蔵されている」という事を覚えておくだけでも次回見に行くきっかけになるのでオススメです。
メインが刀装具ではありませんが日本美術刀剣保存協会が定期的に開催している鑑賞研究会もオススメです。
全国に支部があるので興味のある方は参加してみてはいかがでしょうか。

誰が見ても感動できる彫金の超絶技巧の数々
彫金を独学していて美術展を見に行った時に「勉強になる。」というと「あなたは勉強にできるほどのレベルなのwww?」と言ってくる方がたまにいますが(実体験)、誰が見に行っても勉強する気があれば勉強になります。
インターネットが発達してきたので検索すれば画像をいくらでも見られる時代になりましたが、その彫りの深さや彫り面の滑らかさ、あえて残してあるタガネの跡は実際に見てみないとわかりません。
じかに見る場合は自分で見る角度を変えることで自分なりに情報を拾う事が出来ます。
筆者自身はコレクターではないので過去の有名な彫金師・金工師というのは刀装具の特集本に載っている程度しか知りません。(※それほど覚える気もありません。)
楽しみながら知識を吸収できるのが美術展の良いところ
楽しみながら知識を吸収できるのが美術展の良い所です。
小学生の時に無理やり連れていかれた社会科見学と違って自分が興味を持ってわざわざ行くので十中八九楽しめます。
美術展に行き慣れている方の場合は展示方法や展示物の内容にガッカリすることもあるかもしれませんが、そんな方は稀でしょう。
例えば光村利藻が自身のコレクションを収めるための指物(箪笥みたいなもの)を指物師に発注したところその指物師は10年間家に帰れなかったというようなエピソードも実際に膨大なコレクションの量を見ながらその説明を読むだけで「これは大変だったでしょうね…。」と想像を楽しむことができます。
現代の金属事情などを加味して鑑賞する楽しみ
「鏨の華」で展示されている刀装具の数々は明治時代のものが中心になっています。
光村利藻が明治時代の偉人なので当然ですが、明治以前の作品というのも当然あるのでその意匠の変化というのを見るのも楽しい点です。
筆者はこういった美術展を見に行った時にいつも考える事ですが、昔の彫金師が現代の金属や技術などを見た時にどのように利用するかという事を考えます。
例えば江戸時代の金工師は糸鋸作業の時に滑りをよくするために蝋やテレビン油を使ったようですが、筆者は管理の簡単さなどからラスペネ(潤滑油)を使っています。
おそらく江戸時代にラスペネがあったら当時の金工師は喜んで使っていたはずです。
そもそも現代の彫刻台の形が一般的になったのはごく最近だそうで元々は木の棒の先端に松脂をつけ、そこに彫金対象をくっつけて作業していたようです。(※出典「超技法 桂盛仁の彫金」)
現状筆者が仕事で受けているようなステンレスのような高硬度の金属というのもなかったわけですから、現代との違いを考えながら鑑賞するのもいいかもしれません。

IMULTAでした。
それでも独学でやってみたい方はこちらの電子書籍をご覧ください。
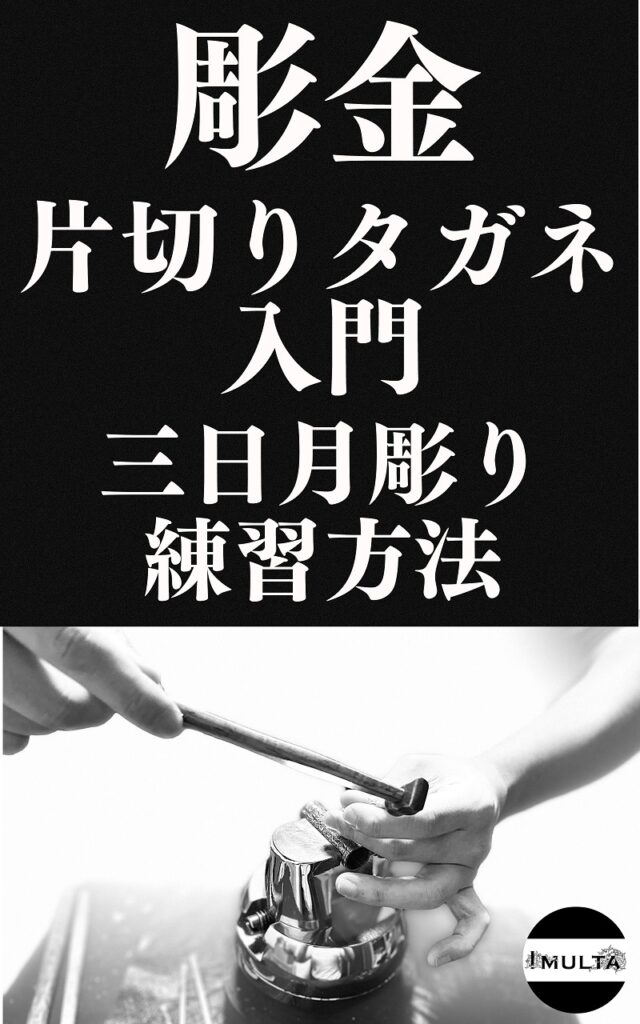
\IMULTAの読む彫金教室のサポートをお願いします/
いただいたご支援はブログとYOUTUBEチャンネルの運営に当てさせていただきます。

🔥 ブログで紹介した技術を詰め込んだエングレービングアイテム
IMULTAでは、今回ご紹介した技法で仕上げたシルバーアクセサリーを販売中!
手作業ならではの精緻な模様を、ぜひ手に取ってご覧ください。

商品はこちらからご覧ください。→https://imulta.shop/