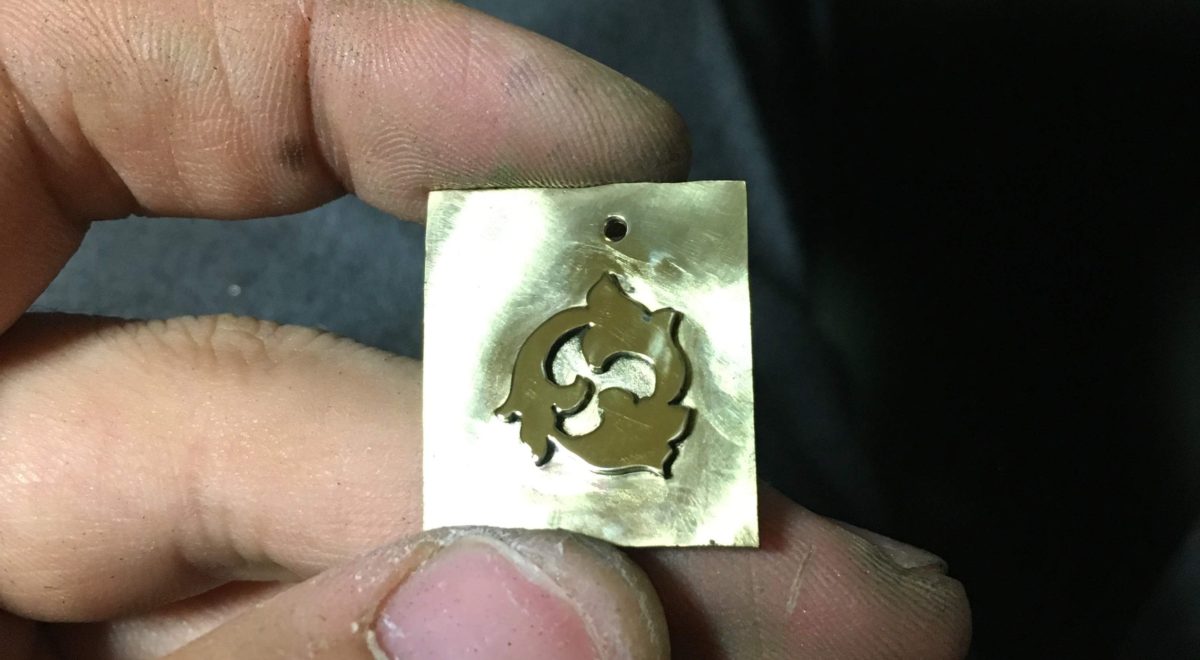今回は前回のアニミズムの少しあと、大きな宗教が出来てそこから派生した装飾からの考察です。
前置きしておきますがいずれかの宗教が優れているという話ではなく、それらの宗教に関する装飾が「伝播していく中でこんな変遷や影響があると考えられるよね。」という話をします。
装飾の起源を探ると、しばしば「アニミズム」──自然物や動物に宿る精霊や神秘を信じる古代の信仰──に行き着きます。
しかし今回は、その次の段階、つまり“大きな宗教”が生まれた後の時代に焦点を当ててみたいと思います。
繰り返しになりますが、本記事の目的は特定の宗教を礼賛したり批判したりすることではありません。
むしろ、それらの宗教がどのように装飾に影響を与え時代や地域を越えて伝播していったのか──その過程に注目し、「意匠の言語」としての装飾の変遷を考察していくものです。
ちなみに私は一応実家が浄土宗(檀家というか親戚が寺をやってる)ですが基本的に節目の行事以外は仏教徒らしいことをやってはいないのでほぼ無宗教ですし、それぞれの宗教の教義について詳しくはわかっていません。
それぞれの宗教が広まった土地土地の気候や気候地形によって見えてくる装飾の雰囲気を楽しむための内容になります。
私はその時代ごとの識字率など文化風俗を考えて装飾の成り立ちや浸透した経緯を考察するのが好きなので、それぐらいのカジュアルな感覚でご覧ください。
まとまりきらなかったのでちょっとずつ加筆します。
装飾と宗教の出会い
宗教が体系として成立し、広く民衆に伝播していく過程で、視覚的な象徴や装飾が果たした役割は極めて大きなものでした。
自然崇拝(アニミズム)の段階では木や石、骨などに刻まれた模様は「霊」を呼び寄せるための媒介であり、装飾というよりも“まじない”や“呪術”の意味合いが強いものでした。
しかし宗教が体系化され「教義」や「神の概念」が言語化されると、それに伴う「見える象徴=装飾」が求められるようになります。
言葉では説明しきれない超越的な存在や真理を、人々が“見る”ことで理解するためには絵画や彫刻、建築の装飾が必要になったのです。
装飾は教義の象徴であり、また教えを広めるための“語らない言葉”でもありました。
また各宗教が誕生したころは識字率が低く、紙などの情報を伝えるための道具自体が希少なものだったので文字で広めるのは単純に効果が低いというのもあります。
神殿の柱に刻まれた文様、僧侶の衣に織り込まれた刺繍、祭具に施された金属細工──それらはすべて「信仰を形にする技術」として進化してきた歴史があります。
宗教以外の視点を入れると日本の彫金技術が飛躍的に進化したのは武士の台頭に伴って鎧や刀の需要が高まったたという背景があります。
それぞれの土地の社会がどのように形成されているかで何をもって彫金やそのほかの装飾技術が進化したかというのが違ってくるのは面白いですね。
宗教ごとに異なる「禁忌」と「美」
宗教が異なれば神や聖なる存在に対するアプローチも異なります。
そしてその違いは装飾の“あり方”に顕著に現れます。
それぞれの時代における政治的な背景があるのでいろいろと見方があると思いますが、あくまで装飾としての視点を書きます。
◆ イスラム教:幾何学文様とアラベスク
イスラム教では偶像崇拝を禁止しており、人や動物の具体的な姿を神聖な空間に描くことを避けてきました。
その代わりに発展したのが、精緻で無限に反復する幾何学模様や植物的な唐草模様(アラベスク)です。これは「神の完全性」や「永遠性」を、象徴的な形として表現したものです。
Instagramで中東系の方で幾何学模様を描かれている方を見ますが、描き方自体が同模様を反復して描きやすいように設計された装飾体系です。
対象を全体的に装飾することに適した技法なので空間の世界観が形成しやすい特徴があります。
そこから考察すると文化的な思想が簡単に崩れない確固たるアイデンティティを感じさせる文化の土壌となっています。
唐草模様の日本への伝播
日本の唐草模様というと風呂敷の柄を連想する方が多いと思いますが唐草模様は中東からアラベスク模様が伝播して現在の形になっています。
中国との交易で仏教経由で伝わってきており聖武天皇のオタク部屋でおなじみ正倉院に収蔵されているものには「葡萄唐草」の装飾が入った台があるので奈良時代には日本に伝わってきていたようですね。
◆ キリスト教:具象的な聖像と象徴性
キリスト教は神や聖人の姿を視覚的に描くことを通して「福音(良き知らせ)」を伝える文化です。ステンドグラス、フレスコ画、彫刻──特に中世ヨーロッパでは、識字率が低い民衆に向けて、聖書の物語を“見る”ことで理解させる工夫が凝らされました。
ただ実際にはカトリックが教義を広めるために絵画を用い始めたようなのでキリスト教も最初は偶像崇拝禁止でした。
4世紀:コンスタンティヌス帝による公認以降
313年の「ミラノ勅令」でキリスト教がローマ帝国で公認されると、「信仰を広げる手段としての“視覚表現”」が重視されるようになります。
識字率の低い民衆に教義を伝えるために、イエスや聖母マリアの具象的な図像が登場し始めます。
その土地の人が教会に来た時にステンドグラスや絵画を見てキリストやマリア様について理解を深めるといった形です。
ルネサンスの前の中世ヨーロッパの絵画は修道士が描いたもので、あえて下手に書いているという説もあり本当か嘘かわかりませんが非常に面白いですね。
筆者はただ下手なだけだと思っています。
偶像崇拝に関しては現在でも聖書至上主義のプロテスタントのように絶対認めないという宗派もいますが容認されているような状態で、少なくとも8世紀のビザンチンの聖像破壊運動(イコノクラスム)のような問題は起きていないようです。
現在では装飾の飾る・空間を彩るという機能以外がそれほど重要視されることはないと思うのですが、大昔は識字率が低かったこともあり思想の伝達手段や教育に大きな役割を持っていたというのが、現代との大きな違いでありながら近年のピクトグラムが似たような機能を持っているというのが歴史の連続性を感じさせて非常に興味深いですね。
ピクトグラム(pictogram):言葉を使わず、絵や記号だけで情報や意味を伝える視覚的な図記号
- 🚻 トイレの男女マーク
- ⛔ 進入禁止のマーク
- 🔥 火災報知機の案内
- 🛫 空港の搭乗ゲート案内
- 🏃♂️ 非常口の「逃げる人」の図
要するにぱっと見でわかるマークのことです。
キリスト教の普及は装飾発展に大きな影響力があった。
彫金の実演配信で頻繁に話に出している彩色写本、ケルズの書やリンディスファーンの書といった有名な彩色写本をはじめ表紙だけでも非常に豪華に彩られた写本が多くあります。
これは権威を高めるために豪華に装飾されているものですがキリスト教の装飾とケルト文化の装飾が混ざり合った特徴的な構成になっています。
ケルト系の文化圏にキリスト教が伝播するにあたり注目されるのが太陽十字(ケルト十字)という十字架に円がついたモチーフで現在では一般的なクロスモチーフの中の一つになっています。
これはキリスト教が伝播する前からケルト文化圏に存在していたとも言われています。
キリスト教という宗教本体とは離れた何か遠因的な要因で十字架だけが先に伝播して生まれたという事も考えられるので、それだけ宗教というものの影響力の大きさを感じさせられます。
ただ一般的には太陽十字とキリスト教は関係ないとされているらしいです。
あんなに似ていてそんなことあり得る?というのが筆者の印象です。
◆ 仏教:蓮華文・曼荼羅・象徴的動植物
仏教では悟りや宇宙観を抽象的な形で表現することが重視されます。たとえば蓮の花は「泥の中から美しく咲く清浄さ」の象徴。
曼荼羅は世界観を可視化したものであり、それ自体が一つの宇宙です。
仏教の装飾は、宗教的な世界観や哲学を伝える高度に抽象化された「図像言語」として発展していきました。
伝播と変容──意匠が宗教を越えて旅する
装飾は宗教とともに広まりながら、地域ごとに姿を変えていきました。これは「宗教の布教」が同時に「装飾の伝播」でもあったことを意味します。
例えば、インド仏教の蓮華文様は中国を経由して日本に伝わり寺院の装飾や仏具の文様に定着しました。
アラビアの幾何学模様はスペインを経由してヨーロッパ建築に影響を与え、ルネサンス期にはそれが植物的なアカンサス文様として再構成されます。
また絹や香料などとともに“文様”もシルクロードを通じて移動しました。
装飾が宗教を超えて旅をすることで、もともとの意味が変わったり抽象化されたり、単なる「美」の要素として定着することもあります。
ある模様を見たとき、「これは○○宗教のもの」と即答することができないのは、こうした長い伝播と変容の歴史があるからです。
余談ですが伝播した先での独自の進化・発展の特異性にこそ、それぞれの民族のアイデンティティが含まれていると考えています。
色んな意匠がありますがベツレヘムパールなどは独特な存在感を持った伝統工芸の典型例だと思います。
装飾に宿るのは「祈り」か「美」か
時代が下るにつれ宗教的な意味合いを持って生まれた装飾も、その「信仰としての中身」が徐々に抜け落ち、純粋な「美の表現」として扱われるようになっていきます。
たとえば、アカンサス模様はギリシャ・ローマ時代の神殿建築に起源がありますが、現代では宗教性よりも「装飾性」として親しまれています。蓮華文様も仏教に由来するものですが、ファッションやアートの分野では宗教性を感じさせない形で使用されることがあります。
しかしそれらの模様に私たちが「なぜか惹かれる」「美しいと感じる」理由は、無意識のうちに宿る“祈りの記憶”が影響しているのかもしれません。
それは遥か昔の人々が祈りや恐れ、感謝とともに刻んだ意匠が時代を越えて今の私たちに届いているからこその感覚と言えるのではないでしょうか。
彫金や装飾に込められた“美しさ”は、決して技術や図案の洗練だけではなく、そうした「祈りの痕跡」を纏っているからこそ心に響くという一面があるのでしょう。
まとめ
宗教という“信仰のかたち”が形成され装飾という“視覚表現”と出会ったとき、そこには人間の美意識と祈りの両方が刻まれるようになりました。
人類の宗教における装飾とは単なる美ではなく、「見えないものへのまなざし」が形を持ったもの。
現代の装飾にも、そのルーツを辿れば祈りや信仰の記憶が眠っている──そう考えると、身の回りの模様や意匠が、少し違った風に見えてくるかもしれません。
それぞれの地域の装飾の特異性というのは、その土地に住む人々のアイデンティティを形成してきたと考えるとより深く理解したくなった時の視点の転換に役立つかもしれません。
宗教的な決まりの中での装飾、ファッションとして、身分や権威を表すためのものとして。
彫金だけではなくあらゆる装飾は生活に根差しているという事が今回の宗教に伴った伝播からもわかるのは興味深い事ですね。
🔥 ブログで紹介した技術を詰め込んだエングレービングアイテム
IMULTAでは、今回ご紹介した技法で仕上げたシルバーアクセサリーを販売中!
手作業ならではの精緻な模様を、ぜひ手に取ってご覧ください。

商品はこちらからご覧ください。→https://imulta.shop/
\IMULTAの読む彫金教室のサポートをお願いします/
いただいたご支援はブログとYOUTUBEチャンネルの運営に当てさせていただきます。